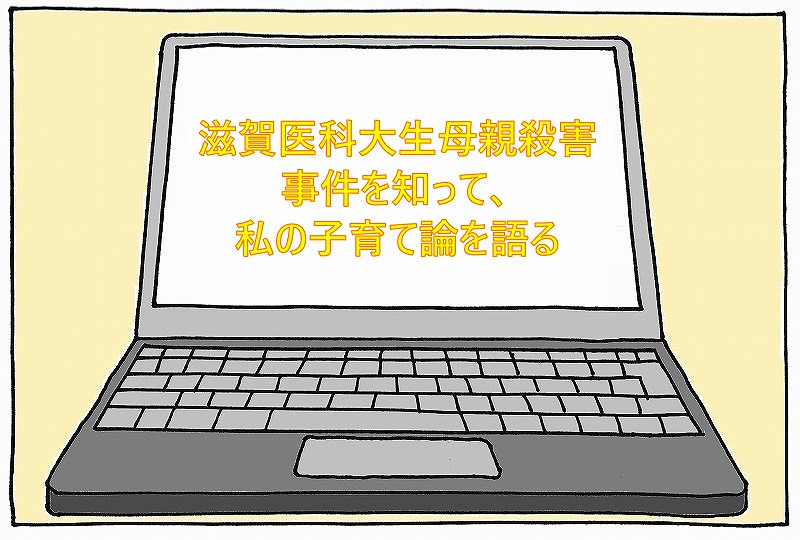なんとも言えない気持ちになる事件を知りました。
今年の年初頃からYoutubeで動画がちらほら上がっていたのは知っていましたが、きちんと内容を見ていなかったので、先日いくつか視聴してみました。
これでもかってぐらい大雑把に言うと、教育虐待が原因の事件です。
母親に医学部に行くことを強要された娘が9浪の末、母親を手にかけてしまったという、筆舌に尽くしがたい内容です。
私は子を持つ親の立場ですが、全面的に娘さんの味方です。
今は服役中だと思いますが、出所後の新たな人生では、過去を忘れ幸せに過ごして欲しいと願ってやみません。
自分に子供ができてから、子育てに関するコンテンツを気に留める機会が増え、その都度自分の考えとは合わないなぁとよく感じてきたので、これを機に私の子育て論を書き綴ってみようと思います。
誰の参考になるかは分かりませんし、私の考えがこの世で最も正しいなどと勘違いはしていないですが、色々な子育ての考え方に関心のある方は是非一読してみてください。
それでは本題へ。
滋賀医科大生母親殺害事件の概要
子育て論を語る前に、まずこの記事のタイトルにある事件を少し説明します。
この事件は2018年に起こったそうで、教育虐待を受けていた女性(当時31歳)が虐待をしていた母親を殺害した事件です。
母親は娘を医者にしたいと熱望しており、地元国立大学の医学部受験を9回も受けさせ続け、医学部看護学科に進学したものの看護師になる事を認めず、再度、助産師を受験するよう命じた結果、娘の我慢が限界を超え、殺害に至ったとのこと。
これだけであれば殺意として、やや弱そうに見えるかもしれませんが、この母親は娘の行動を厳しく制限しており、一例として、スマホの所持を認めず、隠れて持っていたのを見つけた際には目の前で破壊し、土下座までさせて謝らせていたそう。
この母親自身、最終学歴が高卒で学歴コンプレックスを持っていたことも教育虐待に拍車をかけた要因のようで、自分と同じような道は歩ませたくないと常々話していたそうですが、医者限定の進路を強要し、且つ、地元国立大学一択と、娘に選択肢を与えず、不合格であったにも拘わらず、周囲に合格したと嘘をついていたところを見ると、娘の学歴や進路を自身のステータスにしようとしていたように見えます。
昔、一時期話題になった子供4人が東大に進学した佐藤亮子氏と同じ、子供をアクセサリーと思っている親の典型のように感じました。
この佐藤亮子という人物も、私はあまり快く思っていません。
4人の子供たちはとても立派だと素直に思いますが、それは子供たちの不断の努力の成果であって、この母親の手柄ではありません。
にも拘らず、さも自分の功績かのようにテレビに出たり、本を出版したりとする姿が浅ましく、自分の親や妻がこんな人間だったら本当に嫌だなと思った記憶があります。
私の認識では、この人物は、子供を使って世間からの羨望の眼差しを自分に向けさせたかっただけの自己顕示欲の塊だと思っています。
話がそれてしまいましたが、他にもこの事件の母親は、到底親がすることとは思えないような行動をとっており、娘さんの動機は十分理解できます。
詳しく知りたい方は、Youtubeあたりで検索してみてください。
子供は親を選べません。
歪んだ人格の親だったこの事件の娘さんには、同情の念を禁じえません。
繰り返しになりますが、出所後は母親の事は忘れて幸せになって欲しいと思います。
子育てにおける学業に対する私の考え
ここからは全て私の個人的な考えです。この考えが必ずしも正解とは言いません。異なる考え方で、子育てを終えた先人たちの子供たちも社会で立派に生活していますから。
なので、たくさんある中の一つの考え方として捉えてください。
私は、小学校から大学までの学業は、社会にでて仕事をして生きていく上でとても重要な要素だと、私自身の経験から感じています。
但し、重要なのは学業に真剣に取り組む経験であって、最終学歴の高低はあまり重視していません。
結果を軽視しているのではなく、学歴としては地方の国公立大学に受かるぐらいまでになれば上出来と思っています。
学部も医学部などの難関ではなく、工学部などで十分で、このぐらいのハードルであれば、小学校から高校までの12年間、周りの人たちよりも、ほんの少しだけ努力し続ければ達成できる水準です。
私は自分の子供たちには、常々、どこの県でも良いから国立の大学に行くんだよと言っています。ですが、具体的にどこの大学を目指せとまでは言いません。
また、文系理系の選択も子供の希望に任せています。
なぜなら、私も妻も子供を自分たちの思い通りにコントロールしようという意思はないからです。むしろ子供の人生なので、子供たち自身でどんな道を歩むか自発的に選んで欲しいと思っています。
ここまででお分かり頂けると思いますが、私が重要と考えているポイントをまとめると大きく下の2つです。
- 学業を頑張る事は必要。
- 進路は子供自身が決める。
この2点について、詳しく説明します。
学業を頑張る必要性
私の経験から社会人になって人並みに稼ぐためには、新しい何かを生み出す創造力と、問題解決の能力が必要だと感じています。
どちらの能力も必要で、社会人として、勤め人でも自営業でも恐らく変わりません。
成功する人は、この創造力と問題解決力がとても優れているように思います。
この2つの能力は、先天的に持って生まれるものではなく、10代の頃に適切に訓練すれば誰でも一定の水準まで身に付けることができると思っています。
その訓練として学業を頑張る事は、非常に有効だと私は考えています。
学校で習う勉強は、特に問題解決の能力を鍛えるのに効果的で、数学や物理、化学などが分かりやすいと思います。
数学の問題を解くには、問題文で問われている内容を理解し、適切な公式や定理を用いて答えを導き出すわけですが、社会に出てもこの手順は、どんな場面でもほぼ必要になります。
仕事の上で問題が起こった場合でも、何が問題なのか?どこに不具合があるのか?を分析して理解し、過去に似たトラブルや、または参考になりそうな成功例が無いかを調べ、応用して目の前の問題の解決に取り組みます。
社会にでてから直面する問題は、学校のテストとは違い明確な答えはありませんが、それでも一定の水準以上の学歴のある人たちは、この問題解決能力が高い傾向があり、それは学業に取り組むなかで問題解決に必要な思考法がしっかり身についているからではないかと、いつも感じています。
更に言うと学業を頑張って取り組むと、自然と調べる能力も身に付きます。
学業に取り組む事で身に付く能力や思考法は、社会に出てからも有効に活用でき、且つ必要になるものであるため、私は子供たちに学業をしっかり頑張って取り組ませています。
一方で新しい何かを生み出す創造力も学業に取り組む事で育まれると考えています。
創造力は、個人の持って生まれた才能のように捉えがちかもしれませんが、決して才能のみに依存するわけではなく、どれだけたくさんの情報を持っているかが重要です。
私は製造業のエンジニアとして20年以上仕事をしていますが、製造業に限らず、音楽でも絵画でも、過去の偉人の作品を何も知らず模倣もせずに、全く新しいものを創り出すのは、まず無理だと思っています。
どんな人でも過去の作品からヒントを得たり、参考にして発展させたり、既にある別のモノを融合したりして、新しいモノを作っています。
なので、どれだけの知識があるか?情報を持っているか?が創造力の源泉であり、学校で習う全ての科目は、この知識や情報を身に付ける有効なきっかけになるのです。
また、少し私の経験を元に、学業を頑張って取り組んで良かったと感じた具体例として、社会人になってから資格試験を受ける際に、学生時代に多少なりとも勉強していた分野であれば、難関と言われる試験であっても結構すんなり合格できます。
私が取得した資格は、第3種電気主任技術者とエネルギー管理士(電気分野)といった、そこそこの難関資格から、簡単なボイラー技士2級や危険物取扱者乙4などで、ボイラー技士と危険物の資格は、試験日の前々日から2日ぐらい参考書を読んだだけで合格しました。
これも学生時代に、学業にそれなりに取り組んでいたことの延長で、周囲の人は驚いていましたが、私の感覚だと、そこまですごい成果とは思いません。
これらが十代のうちに学業をしっかり頑張る理由だと私は考えていて、私の子供たちには機会がある都度、この話をしています。
子供の進路は子供自身に決めさせる
当たり前の事ですが、親と子供は別の人間です。
親が子供の人生を決めてはいけません。子供の人生を決めるのは、子供自身です。
その前提で親がしないといけない事は、子供が自身の進む道を決めようとする時に、その方向に進むために必要な土台を与えておく事です。
子供が進みたい進路があっても、学歴や知識がないため進めないといった事にならないように、幼い頃から親が将来のための手助けをしておくというのが私の考えです。
前章の学業の必要性の話の続きのようになりますが、世の中のほとんどの人は、幼い頃から自発的に勉強に取り組んだりしません。
なので、子供が幼いうちは、親が隣に座って一緒に勉強に取り組みながら、勉強する習慣を身に付けさせ、中学生や高校生になった頃には、自発的に勉強に取り組むようになるよう意識しています。
更には、勉強の取り組み方も、誰かに教えてもらうのを前提にするのではなく、分からない事や知らない事は、まず自分で教科書や参考書を読んで調べ理解するように努めさせ、それでも解決しなければ、私たち親や先生などに聞くようにさせています。
但し、この勉強のやり方では、どう頑張っても東大・京大などの難関大学には届きません。
小、中学校までは、子供の分からない問題は、ほとんど親が教えているので難関校の受験に特化したような進学塾で習うほどにはならないのです。
それでも我が家は、子供たちに極端な学歴を求めていないことと、子供たちが苦痛に思うことなく勉強に取り組み、1度しかない学校生活で、友達と遊ぶ時間や部活を楽しむ時間を十分確保できるよう、このやり方をしています。
重要なのは、学生のうちに、自助努力の重要性を理解して欲しいと思ってこうしており、ある程度の水準の学力と、自助努力ができる人になっていれば、社会に出てから、仕事についていけないとか、通用しない人間にはならないと信じています。
もうちょっと言うと、学校を卒業したら、仕事であっても一から十まで誰かに教えてもらえるなんてことはありません。
何事も自力で学び、身に付けるという考え方を社会に出る前に身に付けさせたいんですね。
私の子育ての考えでは、子供が大人になって手を離れた後は、自力でしっかり生活していけるようになってもらう事が最も重要なのです。
そして子供の人生は子供のものなので、子供自身が望んで選んだ世界で楽しく活き活きと生活して欲しいと思っています。
なので、子供の進路は子供自身に決めさせる。親はよっぽどの進路でない限り口出ししない。
これが私が大切にしている考え方です。
私がこの子育て論に至った理由
前章まで私が子育てをする上で大事にしている考えを書き綴ってきました。
一部説明不足な部分もありますが、あまりにも懇切丁寧に書くと長すぎるので、だいぶ主張したいことの要点を絞っています。
ここまで読んでくれた読者の皆さんには、私の考えがおおよそ伝わっていると思うので、今度は、なぜこのような考えに至ったのかを説明しようと思います。
私は新卒から現在まで、製造業の会社に勤めており、そこでは色々な経歴の人が働いています。院卒、大卒、高卒など。
また、勤務する時間もさまざまで、常日勤と呼ばれる朝8時から夕方5時までの人もいれば、シフト勤務で深夜から早朝までの時間帯に働く人もいて、シフト勤務者は、ローテーションによっては土日が出勤になります。
仕事の内容や勤務形態は会社側が一方的に決めていて、ほとんどの会社が、学歴を基準の一つとして振り分けています。
その振り分けの最たる例が、総合職と一般職の区別です。
今ではあまり聞かなくなりましたが、私が就職した頃では、まだ総合職と一般職で隔たりがあり、入社式さえ分けて行われていました。
当時、私を含め総合職で入社した新入社員は、入社式で幹部候補生と激励され、入社後の等級も一般職より3階級上からのスタートだったので、入社後の昇給額でも一般職の同期と差がありました。
学歴によって明確に差が分かれる「学歴フィルター」は今もしっかり存在しており、今後もっとその差は顕著になると思っています。
新卒の頃から扱いの違いを感じていたことに加え、年齢を重ねて立場が上がるにつれて若手の面倒を見る機会が増え、考えさせられる場面に多く出くわしました。
私は転職を2回しています。
2社目に入った会社では、会社の規模と部署の仕事内容から、工業高校卒の子が部下になる機会がたびたびありました。
その子たちに共通する残念な特徴として、私が一般的と思っているような言葉や表現が通じません。
高卒で入ってくる子たちは、お世辞にも義務教育レベルを十分学習してきたとは言えず、どの子も国語力が低いのが特徴です。
国語に限らず、他の科目も同様に不十分ですが、特に会話での理解力と文章力は社会人レベルではないと思えるほどで、コミュニケーションが取れない事があったり、ビジネス文書が満足に書けません。
但し、イマイチだなと思う相手は高卒の子ばかりではなく、大学を卒業している子であっても、残念な子はいました。
その残念な子たちの共通点は、仕事に限らず、どんなことでも教えてもらえるのがあたりまえと思っているところです。
もちろん会社の仕事は、ほとんどがその会社だけで必要となる知識や技術、ルールなどで、家庭や学校で習うことではないので、教えてもらわないと出来ないのは当然です。
最初のうちは、どの子に対してもできる限り時間を割いて教えていましたが、教えてもらうのを当然と考えている子は、あまり仕事のパフォーマンスが上がってきません。
それどころか教えられていないことをしようとしません。
そういう性質の子だとわかったら、私はあまり面倒を見なくなります。単純な繰り返し作業などしかさせませんでした。
私が一生懸命仕事を教えても、時間を奪われるだけで大した戦力に育つことはありませんから。
当然自立など程遠く、年次昇給の査定も高く評価する事はできませんでした。
昔の職人ではないですが、会社勤めのサラリーマンであっても周りの人の仕事を見て参考にする、または真似するという意識は必要です。
この意識は、仕事に対する向上心ありきかもしれませんが、その前に知識や技術を身に付けるための根本的な思考と、その思考を育む経験不足が大きな原因だと、私は思っています。
こういった常に受け身の姿勢の子たちは、単なる作業員でしかなく、常に誰かに指示される立場のままでいなければいけません。
一度、単純作業員とレッテル張りされると、その評価を覆すのは容易ではなく、いつまでたってもたいした昇給なく同じ仕事を続けないといけなくなります。
そんな勤め人の実情を知っている以上、私は自分の子供たちには、社会に出てから学業をおろそかにした10代のツケを払わされるような事の無いようにしてあげたいと自然と思うようになりました。
そして、私なりに考えた結果が、本稿で書いた子育て論なのです。
まとめ
長々と持論を書き綴ってきましたが、いかがでしたでしょうか?
私の感覚では、放任と教育パパ&ママのちょうど真ん中ぐらいの所じゃないかと思っています。
私の子育て論の根本は、子供たちが大人になってから苦労することなく、少しでも豊かに暮らしていけるように助力することです。
決して、子供を自分のアクセサリーとして周囲に自慢する道具にするつもりはなく、子供たちの幸せな未来を想い、日々頑張っています。
なので、どうしてもタイトルの滋賀の事件の母親のような人物に我慢ができず、この記事を書くに至りました。
私の考えに共感できない人も、もちろんいるだろうと思いますが、世の中にはこんな考えがあるんだなって程度で軽く読み飛ばしてください。
子育ての正解はありませんから。
それでは、長くなってしまったので、今回はこの辺でお開きにしようと思います。